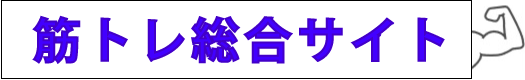ビタミンのはたらき

ビタミンにはエネルギー源として使われたり、からだを作ったりする働きはありませんが、体の機能を正常に保ち、代謝を助ける働きがあります。
「ビタミンA・ビタミンD・ビタミンE・ビタミンK・ビタミンB1・ビタミンB2・ナイアシン・パントテン酸・ビタミンB6・ビオチン・葉酸・ビタミンB12・ビタミンC」の13種類があり、脂溶性ビタミンと水溶性ビタミンに分けられます。
脂溶性ビタミンと水溶性ビタミン
脂溶性ビタミンは水に溶けにくく油に溶けやすく、体内に蓄積されやすい特徴があり、過剰に摂取するとからだに害を及ぼす可能性があるため注意が必要です。油と一緒に摂取すると吸収がよくなります。「ビタミンA・ビタミンD・ビタミンE・ビタミンK」が脂溶性ビタミンに該当します。
水溶性ビタミンは水に溶けやすく、体外へ排出されやすい特徴があり、余分に摂っても尿などから排出されます。長時間水につけたり、茹でたりすると栄養が損なわれ栄養が減ってしまいます。「ビタミンB1・ビタミンB2・ナイアシン・パントテン酸・ビタミンB6・ビオチン・葉酸・ビタミンB12・ビタミンC」が水溶性ビタミンに該当します。
ビタミンA
ビタミンAは脂溶性ビタミンで、皮膚や粘膜を正常に保ち、暗いところでの視力の衰えを防ぐ働きがあります。
ビタミンAはうなぎ・レバー・乳製品などに多く含まれています。
![]()
![]()


ビタミンD
ビタミンDは脂溶性ビタミンで、カルシウムとリンの吸収を助け、丈夫な骨や歯をつくるのに役立ちます。
ビタミンDは魚介類・キノコ類などに多く含まれています。
![]()
![]()
ビタミンE
ビタミンEは脂溶性ビタミンで、脂質の酸化を抑え、動脈硬化や細胞膜の老化から体を守る働きがあります。
ビタミンEはアーモンド・ピーナッツ・植物油・かぼちゃなどに多く含まれています。
![]()

ビタミンK
ビタミンKは脂溶性ビタミンで、血液の凝固に関わる働きがあり、出血が止まりにくくなるのを防ぎます。また、骨にあるタンパク質を活性化して、骨の形成を助けるはたらきもあります。
ビタミンKは緑黄色野菜・納豆・乳製品・卵などに多く含まれています。


![]()
ビタミンB1
ビタミンB1は水溶性ビタミンで、主に糖質の代謝を助けます。また、神経系の正常な働きを保つ作用があります。
ビタミンB1は豚肉・豆類・玄米などに多く含まれています。



ビタミンB2
ビタミンB2は水溶性ビタミンで、主に脂質の代謝を助けます。また、皮膚・爪などを正常に保つ働きもあります。
ビタミンB2はレバー・魚介類・乳製品・卵などに多く含まれています。
![]()
![]()
![]()
![]()
ビタミンB6
ビタミンB6は水溶性ビタミンで、主にタンパク質の代謝を助け、筋肉や血液などが作られるときにも働きます。また、神経伝達や免疫機能の正常な働きを助ける作用などがあります。
ビタミンB6はレバー・肉・魚・バナナなどに多く含まれています。
![]()
![]()

ナイアシン
ナイアシンは水溶性ビタミンで、糖質・脂質・タンパク質の代謝を助け、エネルギーの生産に関与します。また、皮膚を正常に保つ働きもあります。
ナイアシンは肉・魚介類などに多く含まれています。


パントテン酸
パントテン酸は水溶性ビタミンで、脂質・糖質・タンパク質の代謝を助け、エネルギーの生産に関与します。
パントテン酸はレバー・納豆・ピーナッツなどに多く含まれています。
![]()

![]()
ビオチン
ビオチンは水溶性ビタミンで、脂質・糖質・タンパク質の代謝を助け、エネルギーの生産に関与します。また、皮膚や毛髪などを正常に保つ働きもあります。
ビオチンはレバー・豆類などに多く含まれています。
![]()

葉酸
葉酸は水溶性ビタミンで、ビタミンB12と協力して赤血球の生産を助けます。また、タンパク質や核酸の合成に関与して細胞の生産・再生を助けます。
葉酸は緑黄色野菜・レバーなどに多く含まれています。
![]()

![]()
ビタミンB12
ビタミンB12はは水溶性ビタミンで、葉酸と協力して赤血球の生産を助けます。また、神経機能を正常に保つ働きもあります。
ビタミンB12は牡蠣・貝・魚などに多く含まれています。


ビタミンC
ビタミンCは水溶性ビタミンで、コラーゲンの合成や鉄の吸収を助け、ストレスの抵抗力を高める働きがあります。また、抗酸化作用があり、活性酸素から体を守ります。
ビタミンCはレモンやグレープフルーツなどの柑橘類、イチゴ・ブロッコリー・ジャガイモなどに多く含まれています。


![]()
- 関連項目 マルチビタミン